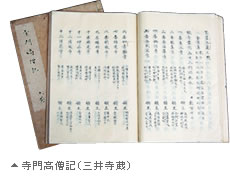覚忠は 元永二年(1118)に生まれ、仁安二年(1167)に園城寺貫首になり、治承元年(1177) に遷化した。増譽から数えたら、三代目の聖護院門主である。応保二年(1162) 閏二月に天台座主に任じられたが、山門から激しい反発を受けた挙げ句、わずか 三日で辞任した。覚忠の三十三所巡礼は『寺門高僧記』のほかに、『粉河寺縁起』 に「久安四年の春三十三の巡禮をいたす」と記されている。「寺門高僧記」においては、行尊の巡礼記と同じような形式で覚忠が応保元年(1161)に行なった巡礼を記録した。その巡礼記は次のように記されている。
一番。紀伊國那智山。御堂七間東向。本尊如意輪一手半。願主羅形聖人。
二番。同國名草郡金剛寶寺。字紀三井寺。御堂五間南向。本尊十一面。願主 為光上人。
三番。同國那賀郡粉河寺。三井寺末寺。御堂九間南向。本尊千手。願主孔子古獵師。
四番。大和國高市郡南法華寺〔字〕壺坂寺。御堂八角五間南向。本尊丈六千手。東寺末寺。願主道基聖人。
五番。同國高市郡龍蓋寺。字岡寺。御室八角五間南向。本尊丈六如意輪土佛。 願主弓削法皇。興福寺末寺。
六番。同國同郡長谷寺。御堂九間南向。本尊二丈十一面皆金色。願主道明并 德道。興福寺末寺。
七番。同國奈良南圓堂。八角東向。本尊不空羂索丈六。聖德太子御建立。
八番。和泉國和泉郡施福寺。字槇尾寺。御堂五間辰巳向。本尊等身千手。本佛彌勒。願主行滿聖人。
九番。河内國丹比南郡剛林寺。字藤井寺。御堂七間南向。本尊等身千手。願主阿保親王(藤井氏)。
十番。攝津國摠持寺。御堂五間南向。本尊三尺千手白檀。并十一面。願主山 蔭中納言。
十一番。同國豐嶋郡勝尾寺。御堂五間南向。本尊五尺千手。願主淨道聖人。 或曰善筭聖人。
十二番。攝津國河邊郡仲山寺。御堂南向。本尊等身十一面。願主聖德太子御建立。
十三番。播磨國賀古郡〔清水寺〕丹波國 多紀郡辻清。 御堂七間南向。丈六千手。願主法道聖人。空鉢聖人也。
十四番。同國印南郡法華寺。御堂九間。本尊等身金銅千手。空鉢之守 佛也 願主空鉢聖人。寶道聖人也。自天降下人仙人云。
十五番。同國餝西郡書寫山。御堂九間南向。本尊丈六如意輪。願主性空聖人。
十六番。丹後國與謝郡成相寺。御堂九間南向。本尊一手半聖觀音。願主聖德太子。
十七番。同國加佐郡松尾寺。御堂九間南向。本尊馬頭觀音。願主若狹國海人 二人建立之。
十八番。近江淺井郡竹生嶋。御堂五間南向。本尊等身千手。願主行基菩薩。
十九番。美濃國谷汲。御堂五間南向。本尊七尺十一面。願主三乃大領并沙門 豐然。
廿番。近江國神崎郡内傘山觀音正寺。御堂五間南向。本尊千手三尺。願主聖德太子。
廿一番。近江國蒲生郡長命寺。御堂七間南向。本尊三尺正觀音。願主武人大臣。
廿二番。近江國三井寺南院如意輪堂。五間南向。願主慶祚大阿闍梨。〔或〕聖豪内供。
廿三番。同國世多郡石山寺。御堂九間南向。本尊如意輪二臂丈六土佛。願主 聖武天皇御願。
廿四番。同國岩間寺御堂。三間南向。本尊千手等身。願主泰朝大師。醍醐寺 末寺。
廿五番。同國上醍醐准胝觀音。御堂五間南向。願主聖寶僧正。
廿六番。山城國東山觀音寺。御堂五間南向。本尊千手。願主山本大臣。基-中納言。弘法大師建立。東寺末寺。新熊野奧有之。
廿七番。同國六波羅蜜寺。御堂五間東向。都内。本尊十一面。亦千手八尺丈六。願主空也聖人。
廿八番。山城國清水寺。都内。御堂九間南向。本尊千手。願主智證大師。
廿九番。同國六角堂。都内。九間南向。本尊如意輪三尺金銅。願主聖德太子。 或記云。金剛三寸如意輪。
卅番。同國行願寺 字皮堂一條。都内。御堂九間東向。本尊八尺千手。 願主道儀聖人。
卅一番。同國西山善峰寺。御堂五間東向。八尺千手。大原野南。願主源筭聖人。
卅二番。丹波桑田郡菩提寺。字穴憂寺。三尺金色聖觀音。願主聖德太子御建立。
卅三番。山城國御室戸山。御堂七間南向。本尊一尺千手。願主寶道聖人。羅惹院僧正。三井寺末寺。
三十三所巡禮 日數七十五日
行尊の巡礼は百二十日をかけ、覚忠の巡礼は七十五日をかけた。巡礼にかかった 日数に四十五日の差があるが、巡拝した霊場はほぼ同じで、現今の西国三十三所 霊場とも一致している。
行尊の巡礼は長谷寺を起点とし、三室戸寺を終点とした。覚忠の巡礼起点は那智山で、現今の一番霊場と一致し、終点は行尊と同じ、三室戸寺である。覚忠の那智山から巡拝しはじめたのは、おそらく彼が聖護院門主として熊野三山と深い関係を持っていたからであろうと考えられる。行尊と覚忠とも三室戸寺を終点とすることは三室戸寺が園城寺の末寺である故と思われる。さらに、彼らの巡礼コースを考察してみれば、現今の第 11 番上醍醐准胝堂から第 33 番谷汲山まで、行尊と覚忠は同じような道順を取ったと見られる。そのうち、第 22 番総持寺から第 30 番竹生島までの巡拝順序は現今とは逆であるが、コースはほぼ一致していると考えられる。また、第 11 番上醍醐准胝堂から第 14 番園城寺までと、第 18 番六角堂から今熊野観音寺から第 21 番穴太寺までのコースも現今の巡礼と類似度が高いと言える。巡礼のコースが院政期にすでにある程度固定されていることを示している。さらに、覚忠の巡礼コースを見ると、現今 の巡礼とは第 4 番施福寺から第 10 番三室戸寺までと、第 31 番長命寺から第 33 番谷汲山までだけに違いがある。宇治にある三室戸寺を終点にした行尊・覚忠の巡礼コースは畿内の人にとって便利なコースである。それに対して、現今の霊場順番は東国の人が巡礼舞台の主役になってから定着した故と考えられる。畿内の巡礼者と東国の巡礼者の道順での差異と見なされてもよい反面、現今の観音霊場巡拝順番は覚忠の巡礼コースから派生したものだと考えられる。それは後に巡礼の先達の中心になった本山派の修験たちにとって、聖護院門主である覚忠自らの巡礼は指標的な性質が帯びておる上、東国の巡礼者にも進めやすいこのコースが標準コースのモデルに見なされたからであろう。